令和4年(2022年)7月19日、
【巡視船しもじ】による誤射事案が発生しました。
前回のつづき
2022年7月19日に発生した、
【宮古島海上保安部】の【巡視船しもじ】における誤射事案についての後編です。
前編において、
私は誤射が発生した長山港の特殊性について述べました。
長山港は人口密集地ではなく、船舶の輻輳海域でもないこと。
さらに、視界がやぶにさえぎられているため、周囲から隔絶されていると錯覚したのではないかと私は推測しました。
そして、その錯覚が乗組員たちの気のゆるみを招いたのではと考えています。
別の言い方をすれば、一般市民や他の民間商船に対する緊張感が欠けていたと思うのです。
ただし、
これは誤射を引き起こした要素の一つに過ぎません。
この事案の背景には【宮古島海上保安部】全体にかかる問題があるように思われます。
さらにこの誤射がもたらした影響についても考えてみました。
後編ではそのあたりを書いていこうと思います。
宮古島海上保安部の歴史
本題に入る前に宮古島保安部の歴史を振り返っておきます。
1972年05月15日
沖縄返還とともに第11管区の発足。
同年10月01日
平良市に平良海上保安署が開設。
2005年10月01日
平良市が市町村合併により宮古島市に。
2007年04月01日
宮古島海上保安署に改称。
2016年10月01日
宮古島海上保安部に昇格。
同年11月30日
1番船【しもじ】就役。
2018年03月19日
9番船【まえはま】就役。
尖閣漁船対応体制の完成。
2020年07月07日
射撃訓練場施設完成、
引き渡しへ。
2022年04月15日
大型巡視船【みやこ】配属。
今年2022年(令和4年)は、
奇しくも【第11管区海上保安本部】発足から50周年です。そして本部発足と同年に平良保安署も開設されています。
そこからかぞえれば、
宮古島保安部にとっても今年は開設50周年になります。
なお、
本部HPには特設ページが設けられています。
宮古島保安部は長らく【海上保安署】でしたが、2016年に【海上保安部】に昇格しています。
これは同保安部を尖閣漁船対応体制の基地とするためで、職員数・船艇数も短期間の内に急増しています。
これ以降、
尖閣諸島周辺海域における対応は次のように分担されました。
・【石垣 保安部】
大型巡視船による中国公船への対応。
・【宮古島 保安部】
小型巡視船による外国漁船への対応。
そして【しもじ】は新造された【規制能力強化型巡視船】の1番船として就役したのです。
なお、
【宮古島海上保安部】については、
過去の【かいほジャーナル】第70号に取り上げられています。
宮古島海上保安部への懸念
以上を踏まえて、
私は【宮古島保安部】に対して次のような心配をしています。
すなわち、
組織規模の急拡大に対して、
組織内部の統制が追い付いていないのではないか?
…という点です。
というのも、
2021年12月に同保安部に所属する海上保安士3人が、大麻を吸引するという事案が発生しています。
(2022年4月に免職処分)
さらに、
2022年2月に同保安部に所属する巡視船内で集団飲酒、機関長が部下職員の顔面を殴打する事案も発生していました。
(その後の処分内容は不明)
これらの事案と今回の誤射はそれぞれ別個の問題です。
しかし、
短期間の内にこうも不祥事が連続しては、そこに共通する規律のゆるみを感じざるを得ません。
すなわち組織としての規律統制が行き届いていないのでは、という懸念です。
さて。
もし本当に統制弛緩があるとしたら。
その背景に【石垣保安部】との違いがあるように思われます。
これは私の主観なのですが、
【石垣保安部】は尖閣警備の最前線として、マスメディアにも取り上げられることが多いです。
一方で【宮古島保安部】については、
そのような世間の認識は薄いのではないでしょうか。
先日の大型巡視船【みやこ】の配属でこそ注目されましたが、むしろそれまで【宮古島】は目立たない存在だったと言えないでしょうか。
同じ尖閣問題に対応しながら、
世間の注目度は低い。
そこに職員の慢心あるいは弛緩が蔓延する余地があった。
そんな気がするのです。
誤射事案の影響
誤射が発生した7月19日の午後、
松野官房長官による定例記者会見において「大変遺憾である」旨のコメントがありました。
その後、
7月22日に斉藤国土交通大臣も記者会見において、同様のコメントを発表しています。
さらに8月9日には、
宮古島市議会からの意見書提出について可決されました。
意見書の採決に当たっては退席者もあったものの、誤射自体については退席者議員も問題視していました。
(粟国恒広議員・新里匠議員の発言参照。)
再発防止の意見書可決
再発防止の意見書可決 海保誤射/18人の全会一致で – 宮古毎日新聞社ホームページ -宮古島の最新ニュースが満載!- (miyakomainichi.com)
海保誤射/18人の全会一致で
野党の4人は退席/市議会臨時会
9日に行われた市議会(上地廣敏議長)では、与党市議から「宮古島海上保安部巡視船実弾誤発射について再発防止を求める意見書」が提出された。この意見書の内容や文言について、一部の野党から不満の声が出て4人が退席。残った与党10人と中立2人、野党6人の合計18人で簡易採決が行われた結果、異議は出ずに全会一致での可決となった。
今回の採択時は、野党1人が欠席していたことから、与野党22人のうち野党で自民会派の粟国恒広氏、平良敏夫氏、我如古三雄氏の3人と保守宮古未来会の新里匠氏が退席となった。
「大事故につながりかねない今回の実弾誤発射については二度と同じことが起きないようマニュアルおよび策定した再発防止作を全職員で順守することを強く求める」との内容で提出された。
新里氏は「趣旨については賛同するが、文言について内容が違う方向に行く懸念がある」との理由で退席した。
また、自民会派の粟国氏も「すでに海保としても対策も安全面についても市長にきっちり報告してあるので、この採決について私たちは退席する」として議場から退席した。
宮古島毎日新聞 2022年8月10日(水)8:59
↑【補足】撮影ミスのためか動画の画面が暗くなっています。
このように、
官邸・国土交通省、宮古島市議会における強い懸念が示されました。
ただ、
それ以上に地元市民の方々の心配と不安は大きかったことでしょう。
ましてやここは島ですから、
「我が島の海上保安部は大丈夫か?」という危機感も一層強いものと想像できます。
たとえば、
私の住む地域にも海上保安部がありますが、「うちの海上保安部!」という感覚は正直ありません…。
しかし、
「離島」では島民全員の生活に海が関係し、それゆえに地元の海上保安部・署を意識する場面が多いのではないでしょうか。
※参考までに島に所在する保安部署を文末に列記しておきました。
宮古島 射撃訓練場のこと
今回の誤射事案について、
第11管区本部の一條正浩本部長は「今回の件で県民の信頼を大きく失墜させたと考えている。」
と述べています。
この「信頼」という言葉で私が思い出すのは、宮古島の南部に建設された屋内射撃訓練場のことです。
宮古島に海保射撃場が完成
宮古島に海保射撃場が完成 県内初、8月から運用 銃器弾薬は保管せず – 琉球新報デジタル|沖縄のニュース速報・情報サイト (ryukyushimpo.jp)
県内初、8月から運用
銃器弾薬は保管せず
2020年7月14日 11:47
【宮古島】海上保安庁が宮古島市 城辺 保良で建設を進めていた屋内射撃訓練場が6月末までに完成した。宮古島海上保安部が12日、地元住民を対象に見学会を実施した。8月上旬から運用開始の予定。尖閣諸島周辺海域の警備力強化を狙う。海保の射撃訓練場として全国4カ所目、県内では初めて。同部所属の約200人のほか、石垣海上保安部や第11管区海上保安部の職員も使用する。
訓練場は県道83号沿いで、建物は道路から約90メートル離れている。地上1階建て鉄筋コンクリート造り。延べ床面積は約695平方メートル。高さ約6メートルで幅約15メートル、長さ約55メートル。壁はすべて吸音材で覆われており、最大25メートルの射撃レーンが5本ある。使用する銃器や弾薬は訓練を行う際に持ち込み、施設内に保管しない。
住民見学会には保良地区の約30人が参加。
同地区自治会の砂川春美会長は「着工からたびたび説明会があり、住民としての要望を伝えた。環境保全、安全性の担保なども含めて私たちの要望が反映されていて安心した」と振り返った。
2020年に、
宮古島の有名なビーチの近くに射撃訓練場が建設されました。
(施設の正式な名称は「浮標置場・訓練棟」のようです。)
建設に当たっては、
地元からの懸念や反対の声もあったようです。
そして、
それは今でも完全に払拭されているわけではないでしょう。
それでも無事完成に至ったのは、海上保安庁側の丁寧な説明と地元の方々の理解があったからと推測します。
まさにそこには地元の方々からの「海上保安庁なら大丈夫だろう。」との信頼があったと私は思うのです。
さらに、
そうした信頼は【平良海上保安署】開設以来50年の間に積み上げられたもののはず。
しかし今回の誤射事案はこの信頼を一瞬にして損ねてしまいました。
改めて、
誤射事案とそれに先立つ一連の不祥事について、私は大変残念に思います。
思い起こせよ梅の花
今回の記事を書いている途中で、気づいたことがあります。
私は【前編】の文中で次のように述べました。
海上保安庁の巡視船艇は、
一般市民や他船と共にあるのが
通常なのです。
この表現によって私自身が気づかされたのですが、これは単に庁舎や係留地の所在のことだけではないと思うのです。
むしろ、
海上保安庁の徽章にも用いられている、
【梅の花】の精神に通じるものを私は感じます。
この梅に込めた海上保安庁:大久保武雄 初代長官の思いを振り返ってみます。
少し長いですが、
お付き合いください。
錨をあげよ 海上保安庁
桜は美しいけれども、花の命は短い。
梅は、寒風の中、百花に先んじて花を開く。
しかも花の香は芳しい。
花が散ると夏のはじめに実をつける。
青梅はふくらんで、暑い夏の日がさすころ、
ちぎられて、ムシロに干され、
秋口に紫蘇といっしょに漬けられて、
重い漬物石をかぶってじっと辛抱し、
頬っぺたを皺だらけにして、
梅干しとなって生まれかわってくる。
そして梅干しは日の丸弁当となって
民衆の腰にぶら下げられる。
すなわち、
大久保武雄『海鳴りの日々 かくされた戦後史の断層』海洋問題研究会 昭和53年8月5日初版 p74より
梅は艱難の中に花を咲かせ、清香を放ち、
花が散っても実を残し、
その実は息長く常に民衆とともに生きている。
これは戦後の民主主義の精神と、敗戦日本が、雑草のようにねばり強く復興していかなければならない民族復興の精神を象徴しているともいえて、私は桜よりも、梅を徽章とすることに誇りを感じた。
たまたま最近『海鳴りの日々』を読み返したばかりだったので、巡視船艇の係留地について考えている内にこのエピソードを思い出しました。
我ながら、こじつけの感はあると思います。
しかし、
第11管区本部の発足から50年という節目の年に、海上保安庁創立の精神を思い起こすのは無駄ではないはずです。
花は咲く
今年の夏はコロナ禍による行動制限がなく、各地の海上保安部において巡視船の一般公開が行われました。
私も久々にこうしたイベントに参加して、身近に海上保安官の方々に接することができました。
本当に久しぶりで楽しく、
こういうイベントってやっぱりいいなーと改めて感じました。
そして、
海上保安庁について市民が見る・市民に見てもらうことが、やっぱり大切なのだとも思いました。
そもそも海上保安庁は犯罪捜査機関でもあるので、その業務内容すべてを明らかにはできません。
言い換えれば、
組織の中に外部からは窺い知れないブラックボックスを抱えざるを得ないのです。
しかし、
そうであるからこそ、一般市民から信じてもらうことが重要になってきます。
業務上の見せられない部分についてすら、「それでも海上保安庁になら任せて大丈夫だ。」と思ってもらうこと。
こうした信頼が市民の中にあれば、
海上保安庁に対する協力を得やすくなり、円滑な犯罪捜査の実現につながることでしょう。
(もちろん他の業務においても市民の理解と協力は重要です。)
では、その信頼はどうしたら生み出せるのか?
というより、海上保安庁が今まで市民の信頼を得てこられたのは何故か?
それは、
海上保安庁は、
常に民衆とともに生きている。

この梅の花の精神を忘れなかったからではないでしょうか。
宮古島海上保安部の皆様には、
今一度、この原点に立ち返っていただきたいと思います。
そうすれば、
組織は必ずや再生し、
信頼という花は再び咲く。
私はそのように信じています。
【参考】
島に所在する海上保安部・署の一覧
・新潟県 :佐渡 署
・東京都 :小笠原 署
・香川県 :小豆島 署
・島根県 :隠岐 署
・長崎県 :壱岐 署
・長崎県 :対馬 部
・長崎県 :比田勝 署
・長崎県 :平戸 署
・長崎県 :五島 署
・熊本県 :天草 署
・鹿児島県:種子島 署
・鹿児島県:奄美 部
・鹿児島県:古仁屋 署
・沖縄県 :那覇 部
・沖縄県 :中城 部
・沖縄県 :名護 署
・沖縄県 :宮古島 部
・沖縄県 :石垣 部




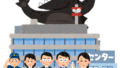
コメント